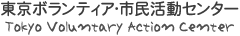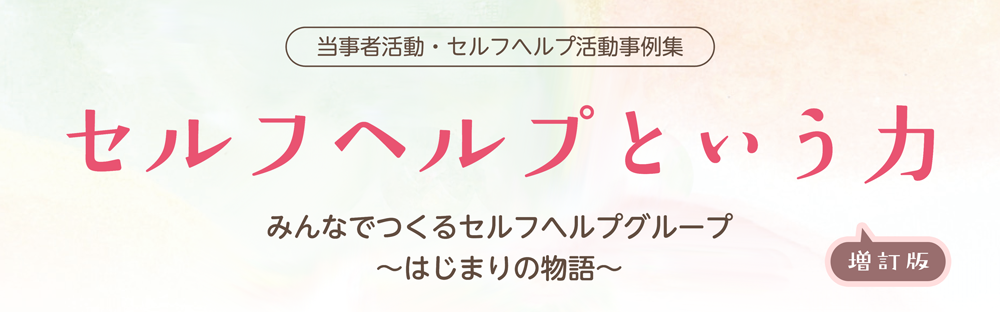lag(ラグ)
今回は、LGBTQ*1、性的マイノリティと理解・関心のある人の居場所づくりに取り組んでいるlag(ラグ)のまさよしさんとゆうさんにお話を伺いました。

心が楽になる場を求めて
まさよしさん
私は普段、LGBTQ、性的マイノリティの方やその周りの人の相談支援に携わっています。私自身はノンバイナリー*2でもあるトランス男性 *3です。性自認はほとんど男性寄りで、ここ4~5年で性別を移行し、今は男性として暮らしています。ホルモン治療をして名前も改名し、男性として過ごすようになってからは、子どもの頃からずっとあった「死にたい」という気持ちはなくなりました。今は息ができるようになったというか、生きている感覚を取り戻してきたような感じです。
幼少期から自分のことは分かってもらえないと、気持ちに蓋をして我慢することが多く、親の期待や他人に合わせたり、異性愛の女性を演じることが長年のクセのようになっていました。小さい頃から感じていた女性を好きになる気持ちを認められたのは、自分の性別違和感を受け入れてから、もう少し後です。苦しかった時期は、少しでも心が楽になる当事者の交流会に参加していました。時間はかかりましたが、交流会に参加しながら自分を受け入れられるようになったことから、女性ではないけれど完全に男性とも言い切れない感覚のことも話せる場所が欲しいと、2016年9月にlagを立ち上げました。今は、戸籍上女性のパートナーと暮らしています。
ゆうさん
私は普段、出版物に関わる仕事をしています。自分はノンバイナリーだと思います。女性であるということは受け入れがたいけれど、男性でもないという感じです。小学校へ入る前から、自分は結婚しないだろう、子どもは産まないだろう、と漠然と思っていました。戸籍上女性のパートナーと、20年近く一緒に住んでいますが、社会的に何も保障もされておらず、こちらから何も与えることはできない、自分が社会に必要とされていない、という感覚があります。
最初は、自分のことをトランス男性だと思っていました。「女性が好き=男性」なのかなと思っていたんです。でも、別に男性になりたいわけではなく、手術もしたくないし、かといって女性として見られるのはすごく嫌だな、という感覚がありました。そんなとき、たまたまテレビ番組を見て、lagの交流会があると知り、参加してみました。
まさよしさん
当時はまだ、男女の二元論に自分があてはまらないと感じている人の交流会(リアル開催)は、そんなにありませんでした。交流会をやってみたら、いろいろな地域から来ていただき、20~30人ぐらい集まるようになりました。人数が多くなるにつれて、次第に一人でやるのが大変になってきたところ、2019年ぐらいから少しずつ、参加者の皆さんが「手伝うよ」と言ってくださり、今は6人で運営しています。
日常生活の中での困りごと
まさよしさん
治療を受けて男性として暮らせるようになる前は、自分の名前を呼ばないで欲しいとか、「お母さん」と呼ばないで欲しい、という思いがありました。私には子どもがいるのですが、子育てをしていたとき、まわりからは「ボーイッシュな女性」として認識されていて、そのたびに「女性ではない」とカミングアウトしてまわるのがとてもしんどかったです。一時期は、家の外に出るのも怖いくらいでした。性別移行してからは、その苦しさがなくなってきた反面、カミングアウトしていない場で過去の話をしづらく、男性として生きてきた体で話す、ということもありました。この他にも、公衆浴場に入れないということや、ホルモン剤が切れて生理が来るとやっぱり希死念慮がおきたりするので、お守り代わりにホルモン剤や飲み薬を確保したりということもありました。
健康診断にはずっと行けなかったのですが、昨年、5年ぶりに受診できました。受付の人がまわりにきこえないように、「性別欄はどちらでもいいので書いてください」と言ってくれ、男性欄にチェックできたことがきっかけになり、「この病院なら大丈夫だな」と受診することができました。ただ、本人確認書類を提示するときは、まだまだ緊張することがありますね。保険証の表面に性別欄が書いてあるので、それを裏面にできないだろうかとか、工夫してもらえると助かることはあります。
ゆうさん
医療関係だと、婦人科は結構きついですね。初診の際に「異性と性交渉して妊娠・出産するものでしょ、戸籍上女性は」という前提を感じ、私のような存在が想定されていないのかと思うと居心地が悪くなります。ただ、職場では、今はコロナのためにずっとリモート状態になっているので救われています。というのも、社長がめちゃくちゃ世話好きで、私に「彼氏いないの?」から始まり、相手がいないとなると、誰かと会わせようとしてくるのです。毎回嘘をつかないといけないので、それが本当に苦痛です。私も「人との接触は必要ない」とか、「恋人はいらない」というキャラを演じないといけない。
参加者が安心を感じられるための工夫
まさよしさん
lagの活動は交流会が主軸なのですが、ノンバイナリーを含むトランスジェンダーの方の参加が比較的多いです。ただ、それ以外の方もかかわってくださるようになっているので、ジェンダーやセクシュアリティに関するマイノリティの人が広く参加できるようにしていきたいと思っています。
交流会では一度も会話したことがないという相手に、いきなり自己紹介しましょうというのは、結構ハードルが高いので、毎回必ず一つはテーマ(服装、カミングアウトについて、好きな映画、音楽など)を決めています。グラウンドルールを設けて、誰もが安全に話しやすいように心がけています。グラウンドルールについては、これまでに7~8回ぐらい話し合いを重ねてきました。毎回、参加者とスタッフのみんなで、交流会の最初に読み合わせをしています。コロナ禍になってからは、オンラインでの開催が中心です。スタッフも合わせて10~15人くらいの参加があります。最近は、インターネットを中心にトランスジェンダーへの差別的な言動がひどく、自分たちも何か発信できればと、オンラインでの映画上映会を先日開催しました。
ゆうさん
オンラインだと、遠隔地から参加してくださる方もいますし、小さいお子さんがいる方でも参加できるというメリットはあります。そのように、ゆるい参加の仕方ができるのはすごくよいなって思います。あと、親御さんが最初に参加して、その後からお子さんが少しだけ参加してくださったということもありました。多分、お子さんが思春期で悩まれていたのかと思うのですが、そのようなオンラインならではの可能性もあるのだと思いました。
まさよしさん
交流会には、子どもである当事者の親御さんや地域の支援者の方が参加してくださることもあります。LGBTQについて勉強したいという方がいらっしゃるとき、当事者からは少し話しづらさを感じた、という声を聞いたことがあります。当事者のみが参加できる場と、さまざまな方が交流できる場を分けるといった工夫をした方がよいのかも、と感じています。当事者とアライ(ally)*4の線引きは、曖昧だと思うところもあるのですが、「安全」の感覚というのも人によって違うので、一番身の危険を感じている人の目線に合わせた方がよいだろうと考えています。
交流会の中では、例えば、健康診断をどういうふうに受けたとか、服を脱がないといけないときはどのような服装であれば胸が目立たずに済だか、などの情報を共有しあうこともあります。性別を移行するための治療の話題や病院での出来事などを話すこともありますね。
ゆうさん
そこで何か有益な情報を得ると言うより、自分の経験を吐き出せる場があることが大事ですよね。他では話せないことだったりするので…それが一番の目的で交流会に来ているのかなと思います。
まさよしさん
あと、距離感は大切にしています。スタッフが仲良くなりすぎることで、参加者が見えなくなってしまうということもあり得ると思っています。お互いが適度な距離感を持ちながら情報交換したり、自分のメッセージを話したりということを大切にしています。別の団体では、差別的な言動をする人たちが来たという例もあるので、万が一そのような場面に遭遇したときにどうするかを、毎回スタッフで話し合っています。内部でのルールをつくったり、シミュレーションなどもしています。お互いに立場が違うと衝突が起きてしまうこともあり得るので、もし感情を抑えられずにぶつけてしまうことがあったらどうするかなど、みんなで話し合っています。
ゆうさん
私は自分自身の当事者性に向き合えるまでに時間がかかりました。人に手を差し伸べることで、本当は自分が助かっているということを、lagにかかわるうちに気づかせてもらったというか、いろいろ学ぶことが多いです。
lagをやっていてよかったと感じること
まさよしさん
lagを立ち上げて個人的によかったのは、つながりができたことです。いろいろな人とのつながりができたこと、同じ体験をしている人同士で知恵を共有しあえる場ができたのは、一番の財産だと思います。また、近隣地域で居場所づくりをしている人たちとのつながりや、他の地域の支援者の方が手伝ってくれることも財産です。
ゆうさん
一口にLGBTQ、性的マイノリティと言っても本当に全然違います。環境も違うし、危険を感じるポイントも全く真逆だったりするので、「同じだね」と勝手にジャッジしてはいけないし、もう一歩、「何でこの人はこういうことを言ってるんだろう」と深堀りしていくと、「ああ、そういうことだったんだ」と普段は見えないことに気づくこともあります。lagにかかわる中で、「これは知っておかないといけない」と思うことが出てきたり、それは自分にも関係があることなので、機会をもらえて本当によかったと思います。
まさよしさん
私自身、一人じゃないっていう感覚を強く持てるようになりました。受けとめ合える場所があるということ、それが一番だと思います。活動を続ける中で、Ⅹジェンダー*5、ノンバイナリーというところに、私自身もこだわりすぎていたのだなと思います。他の団体で相談の仕事にかかわる中で、少しずつ自分の世界が広がっていったような、いろいろな相互作用だと思っています。少しずつ枠が広がってきたような感覚があり、いろいろなセクシュアリティの人が参加してくれるような居場所もできるといいな、と少しずつ思い始めてるところです。
ゆうさん
自分にパートナーがいることを気軽に話せることがどれだけ貴重か、ということを感じています。日常の話を気兼ねなくできることは、これまで経験したことがありませんでした。そういう場所が一つできると自信が出て、今回のような取材でも話せるようになりますし、まず安全な場所があるということが心の支えになっています。
これからやっていきたいこと
まさよしさん
今までの活動をとおしてできたご縁を大切にしながら、スタッフも、それぞれ他の仕事を抱えながらで結構忙しいため、頻度は少し下がるかもしれないですが、なんらかの形で居場所は続けていきたいと思っています。あと、中学校の先生や支援者の方から、講座や授業で話して欲しい、という声をいただくこともあります。そういうときに、lagの他のスタッフが講師になることを、微力ながらサポートできたらいいなと思います。
最近、lagで『といろ』という冊子を初めてつくったんです。これまでイベントでお話していただいた方の特集や、参加者の方々のエッセイをまとめたものです。表紙は、スタッフみんなで集まって、絵具を持ち寄って絵を描き、ゆうさんにデザインをしてもらいました。2年かかってようやくできたのです。労力も時間もかなりかかりますが、地道にこういったものを発信することを、会員の皆さんと話し合いながら、できる範囲で続けていけたらと思っています。
ゆうさん
初めて中学校に行って授業をするという機会をいただきました。自分には子どもがいないから、子どもとかかわることなんてない、と思っていたのです。でも、中学校のときの自分に話すような感覚だったらできるかなと思って、今から楽しみにしています。
まさよしさん
もし、性的マイノリティの方で、一人で悩んでいたり、今いる環境が安全でないと感じる人がいたら、「あなたは一人ではない」こと、「束の間でも安心できる場所がある」こと、「つながる場所がある」ことを伝えたいです。もう一つ、男女別のシーンや生き方の押しつけなどがある環境では、性的指向や性別違和感についてカミングアウトしにくく、我慢してしまう人もまだまだ多いと思います。読者の方で、ジェンダーやセクシュアリティに関心がある方がいたら、まずは知っていただき、安心して生活できる、働ける環境づくりに思いをはせてもらえたらと願っています。
ゆうさん
私は、〇〇らしさのようなものを押しつけられきて、結構大変でした。多くの人が、何かしらの〇〇らしさを押しつけられていると思うので、「もうちょっと楽に生きられたらいいですね」って伝えたいです。

* lag のグラウンドルール。内容はできるだけ簡潔にするよう心がけた。ルールができてから、場の雰囲気がより和やかになったそうだ。

* lag が作成した冊子『といろ』
*1 レズビアン(Lesbian:女性同性愛)、ゲイ(Gay:男性同性愛)、バイセクシュアル(Bisexual:両性愛)、トランスジェンダー(Transgender:出生時に割り当てられた性別と性自認が異なる状態)、クエスチョニング(Questioning:自分自身の性のあり方がわからない、決めたくないなどの状態)の頭文字をとった、性的マイノリティの総称をあらわす概念。レズビアン、ゲイ、バイセクシュアルは性的指向(恋愛や性的欲求の対象がどの性に向かうか)を示すのに対し、トランスジェンダーは性自認(自分自身がどの性に属していると認識しているかをあらわす)を示す概念でもある。
*2 「男性と女性」といった二元論にとらわれない性のあり方。
*3 トランスジェンダー当事者の中で、出生時に割り当てられた性別は女性で、性自認が男性である人たちを意味する。
*4 当事者への理解者、協力者を意味する。
*5 自分自身の性自認が男性でも女性でもないと感じる状態。ノンバイナリーとほぼ同じ意味で使われることもある。
lag(ラグ)
LGBTQ、性的マイノリティや理解・関心のある人ための交流会などを中心に、居場所づくりに取り組んでいる。
毎回、参加する際にはグラウンドルールを読んで、誰もが安心して参加できるよう配慮している。一人ひとりが自分のセクシュアリティを差別されない社会になることをと、lag の活動を続けている。
(キーワード)LGBTQ、性的マイノリティ
運営メンバー 当事者
活動内容
- LGBTQ に関する情報発信
- LGBTQ 交流会の実施
- 勉強会(LGBTQ など)の実施
- オンライン上映会(トランスジェンダーの現状を知る等)
参加できる人
ノンバイナリー、Xジェンダー、トランスジェンダーの方。
それ以外のアライの方の参加も歓迎です。お気軽にご連絡ください。
活動エリア 都内(主に武蔵野市など)
集まれる場 あり(状況によりオンライン開催の場合もあり)
連絡先
Webサイト等
インタビュー:金井聡(相談担当)朝比奈ゆり・海方美雪(編集部)
* 『ネットワーク』383号より(2023年4月発行)