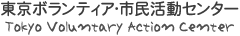助成金申請 5つのステップ
step1: なぜ「助成金」を申請するのか?明確にしよう
- 助成金を申請する上で「どうして助成金が必要なのか?」という理由の説明は不可欠です。確かに「お金がないから」という理由も大切ですが、「お金がない」ならば無理して事業をしなくてもいいのでは、という見方もできてしまいます。
- また「お金がない」状況は他の申請団体も同様です。多くの助成金は、助成団体という第三者からの(団体の存続支援ではなく)「事業」に対する支援ですから、先方に事業の意義と助成金が必要な理由を理解・共感してもらうことが重要です。
- 数ある助成プログラムに手当たり次第申請するのは遠回りです。「なぜこの事業を行いたいのか?」「社会的意義は何か?」「どのような計画や体制で事業を行うのか?」などを団体内で話し合います。そして、その実現のためには「どのような助成が必要か?」を整理し、募集要項をよく読んで理念や目的に見合った助成プログラムを探します。
step2: 助成金の情報を集めよう
- 助成金の情報は様々な形で発信されています。主に以下のような場合があります。
①インターネットで周知
②各助成団体の発行する広報紙やポスターなどに掲載
③新聞の紙面に掲載
④社会福祉協議会やボランティア・市民活動センターの広報紙・掲示板・ウェブサイトに掲載
⑤助成金情報を集めた冊子に掲載
- この他にも助成団体が、臨時に助成(災害発生時や物品寄贈など)を行ったり、新たな助成事業を開始したりする場合も考えられます。さらには、従来の助成内容が変更されたり、年度毎に重視するテーマが変わったりすることもあるため、丁寧に情報収集することが必要です。
助成金情報が掲載されている主なウェブサイト
- 「東京ボランティア・市民活動センター(TVAC)」のホームページ「ボラ市民ウェブ」
https://www.tvac.or.jp/ - 「公益財団法人 助成財団センター(JFC)」のホームページ
http://www.jfc.or.jp/ - 「地球環境パートナーシッププラザ(GEOC)」による運営サイト「環境らしんばん」
http://www.geoc.jp/rashinban/ (主に環境分野)
step3: この「助成を選んだ理由(わけ)」について提案しよう
- 助成団体は積極的に助成を行おうとしています。審査においても「この事業によって、どんな効果が得られるのか」という点に注目しています。
- ポイントは、申請書類を通して「この事業を実施することによって、助成団体が期待する効果を得ることができる」と、具体的な提案や説明ができるかどうかです。
- そのために、過去の助成実績が参考になります。その助成団体がこれまでどんな事業に助成しているのか、内容や傾向を調べ、助成の意図を読み取ることが必要です。過去の助成団体の情報は、助成団体の発行する広報紙やホームページに掲載されていることがあります。
step4: 熱意は表すもの はっきりと文章に表現しよう
- 申請書類の中には「団体紹介ばかりで『何について』、あるいは『何のために』助成を希望しているのかわからない」ものや「その助成を受けてどんな効果があるのか説明されていない」ものもあります。
- 真剣さや熱意の推測はできます。しかしそのこと(熱意をもって事業を確実に行うことができる)が具体的な「文章」として書かれていなければ、審査をする側に理解してもらうのは難しいでしょう。
- 申請書類を作る際、以下の項目について箇条書きにすることをおすすめします。
①団体の目的・活動内容
②申請する事業の内容と具体的な計画
③申請する事業の社会的効果や意義
④その助成プログラムを選んだ理由
⑤希望する助成の内容
- また、申請書類は書き上げてすぐに提出するのではなく、団体のことを知る人と、全く知らない人に読んでもらい、感想をもらい、手を加えていくのも効果的です。
step5: 提出の前に、焦らずもう一度確認 基本が大切
- 完成した申請書類はコピーをとります。審査の段階で助成団体から問い合わせがくる場合もあります。また、万一採択されなかった場合、「なぜ選ばれなかったのか」の分析を行うためにも、申請書類のコピーは重要です。
- 一つの助成プログラムには、多くの団体が申請するため、選ばれるかどうかは、他団体の状況や件数にも左右されます。しかし、「添付書類が揃っていない」「記入や捺印にもれがある」「金額の積算が間違っている」と初めの段階で落とされてしまう例は、意外に多いのです。まずは「基本」をおさえること。当たり前ですが、それが助成金を得る一番の方法です。