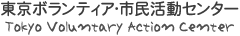助成を受けた次の年
check1: 報告書でアピールしよう
- 助成事業(助成を受けて実施した事業)終了後には、助成団体に対して報告書の提出が必要です。ここでの報告内容は、基本的には「助成金の使途内訳」についてですが、使途が申請内容と異なる、計算のミスがある、領収書の添付がないなど、報告書の不備は意外と多く見られます。助成側にとって報告書は助成した団体の「顔」となります。簡単な内容でも正確・丁寧に記入することが大切です。
- 助成プログラムの中には、一度助成を行なった団体に対して連続した助成をしないものがあります(例えば、申請条件に「直近○年以内に当該助成を活用していないこと」と定めている)。このような場合、再度助成対象となるためには一定の間隔(おおむね3年程度)を置くことが必要です。しかし、過去に助成した団体全てを「対象外」としているものは少なく「2度目はないから、もう関係ない」と、報告書作成の手を抜いてしまうことは、数年後の助成獲得のチャンスを遠ざけてしまうことにもなりかねません。
- さらに報告書は、団体の力量や可能性を助成団体にアピールする機会にもなります。成果のみを一方的に強調するのではなく、事業を通して浮かび上がった新たなニーズや社会的課題、今後の活動の方向性を示すことで団体の意志と積極的な姿勢を表すことができます。
check2: 成果と課題を振り返ろう
- 助成を受けたことが、1回の事業で終わることなく、団体や活動の発展につながるためには、団体内での振り返りがとても大切です。
- その事業は、助成を受ける前と比べてどこがどのように変わったでしょうか。また、団体の役員・スタッフの意識に変化はありましたか?助成事業が終了したら、次のポイントについて話し合ってみてください。こうした議論の積み重ねは、次の活動へのアイデアにもつながります。
| 振り返り(評価)のポイント | 視点 |
|---|---|
| 目標と課題の達成 | ・事業を計画した当初に決めた目標や課題について、どこまで達成できましたか? |
| 残された課題 | ・事業を計画した当初に決めた課題について、達成できなかった課題は何ですか? |
| 新たな課題 | ・団体として新たに取り組む必要がある課題が、浮かびましたか? |
| 新たなメンバーの参加 | ・実施した事業をきっかけに、団体の活動に新たに参加したメンバー(団体役員・スタッフなど)はありましたか? ・団体の使命(ミッション)や、活動の方向性などについて、ともに議論し、考えることができる関係が広がりましたか? |
| 理解者や支援者の広がり | ・実施した事業をきっかけとして、団体の存在を認知し、活動について理解、共感しながら、支援していただける人やグループ、団体などができましたか? |
| 他団体との新たなつながり | ・同じ分野や、関連する活動をしている団体を知り、課題共有や、連携、協力ができそうな関係ができましたか? |
| 新たな社会資源の開拓 | ・今後の活動で、活用できそうな社会資源(人・モノ・金・情報など)を開拓できましたか? |
| 事務局の執行体制 | ・事業実施の上で必要な連絡・調整などの事務についてすすめる体制は、十分でしたか? ・特定の担当者に業務が偏ったり、従来の活動との区別があいまいになってしまったことは、ありませんでしたか? |
| 計画の変更や 新たな決定と合意 | ・助成事業を進める上で、変更(活動日や担当、会議や打ち合わせの日程や内容など)が生じた際、関係者(役員、スタッフ、会員、ボランティアなど)の理解と同意を得る努力を、十分に行いましたか? |
| スケジュール | ・従来の活動と並行しながら、助成事業を実施することについて、スケジュールは守れましたか? |
check3: 事業の成果を多くの人たちに発信する
- 助成事業の成果や内容を関係者や一般市民に向けて、広く発信することも大切です。例えば、総会の中に「助成事業の報告」の時間を設けたり、市民を対象にシンポジウムや学習会などを開催することは、団体が取り組んでいる課題について多様な人と「一緒に考える」貴重な機会となります。
- また、事業の成果をまとめた冊子やパンフレットを作成するのもアイデアの一つです。広く頒布を行うことによって活動への理解を広げることにつながります。多くの人に、自分たちの団体が「何をしたいのか」について理解してほしい場合、実際に今まで「何をしてきたか」の成果を伝えると大きな説得力になります。
check4: 「気づいたこと」とアイデアを出しあおう
- 事業に取り組む中で「次はこうしたい!」というアイデアが一人ひとりの頭の中に浮かんできたことと思います。これらを共有する機会を設けることが大切です。
- 団体のミッション達成のために、現状の活動に工夫を加えたり、新たに必要な活動を生み出したり。そのためのアイデアを出しあい、議論できる雰囲気や環境が団体の中にあることは、助成金を受けるためだけではなく、グループ・団体として成長し続ける上でも重要です。
- 「できる」「できない」の判断は、最後に行えばいいので、アイデアを出しあう場では、メンバー同士がお互いの「ひらめき」や「勘」を尊重しながら、自由に、前向きに話し合うことが大切です。
check5: 「アイデア」を実現に近づける
- 出し合ったアイデアは、まずはすべて「できること」と位置づけます。そして実現のための課題を整理するところから始まります。「何が足りないのか」だけでなく「どうすれば補えるのか」、ひとつひとつのアイデアを最大限尊重しながら、積極的に考えることが求められます。
- 例えば、以下のポイントを参考にしながら、団体内で検討を行なってみて下さい。
①「足りないこと」は何か。また、それらを補うためにはどうすればよいか。
②これまでの経験やノウハウから、活かせるもの何か。
③「活かせる」と考えた経験やノウハウは、そのまま使えるものか。あるいは、形式や方法をアレンジする必要があるか。
④実施する上で、事務局体制や組織体制について、変更する必要はあるか。
⑤団体として、あるいは地域の現状や社会の情勢から考えて、取り組むべきタイミングはいつか。
⑥「人」や「資金」について、団体の自助努力でどの程度工面できるか。その上で、足りない分はどれだけか。
check6: 団体のこれからの姿を描く
- 活動をはじめて間もない頃は、「おもいつき」で何とか活動が成り立っていくかもしれません。しかし、関わるスタッフや参加者が増えてくると、必然的に、組織の課題に対応する機会も増えます。
- また、助成金の申請についても、初回以降、なかなか良い結果が得られず、自分たちの活動に自信をなくしてしまうこともあるかもしれません。
- こうした困難を、単に活動の「行き詰まり」とするのではなく、成長する過程での「試練」として受け入れつつ、打破するために団体の状況を冷静に分析することが重要です。
- 確かに、連続して助成を受けることは難しく、活動が本格的になりつつあるところで、再び資金難に陥ることもあるかもしれません。しかし、それを「自分たちの活動が認められない」と嘆くのではなく、申請書を今一度確認してみてください。すでに活動実績や経験を持つ団体として、「今すべき活動」であり、そしてその活動は「今すべき時期」として明確に書かれているか、さらには、活動の波及効果を示せているか。そのあたりにポイントがあるかもしれません。
- 助成団体は、助成した事業を実施することによって、その団体の活動が充実し、ミッションの達成に近づくための「たしかな歩み」になることを願っています。ですから、過去に助成した実績のある団体が、再度申請をしてきたならば、経験を踏まえた上で団体としての将来像を示しているか、さらには新たな取り組みが具体的に提案できているかを求めています。
- 一方で、助成金だけを頼りにせず、資金面での支援者を広げていくことも必要です。助成事業の成果を踏まえた学習会やシンポジウムの開催は、活動の成果を広く伝える一方で、団体の活動を理解してもらうことを通して、多くの人に資金的に支えてもらうためにも重要な機会です。
- 助成を受けた次の年度は、「今年度の活動費をどう工面するか」に意識が向きがちな時期かもしれません。しかし、この時期だからこそ、団体の未来の姿を描きながら、「目標を実現するには何をするか」について具体的に考えることが大切です。