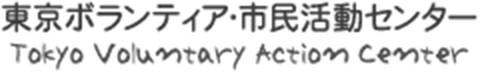しぶやボランティアセンターインタビュー
「しぶやボランティアセンター」とは
しぶやボランティアセンターでは、年代や所属、ライフステージなどに合わせた情報発信を行い、ボランティアの存在を周知することに重きを置いて活動しています。
ボランティアをする人と、ボランティアを必要としている個人や団体へと丁寧につないでいくことで、最終的には、『市民、行政、民間企業、NPO・市民団体など"地域福祉を支える担い手"が、連携・協働するためのプラットフォーム』となることをめざしています。
しぶやボランティアセンター 三者協働の取り組みのきっかけは?
以前より、NPOや地域団体から「何か一緒にやりませんか」とお声がけをいただいていました。「『何か』って何かな」と考えていたのですが、3年程前《災害》をキーワードにやってみようと思いました。これが最初のきっかけです。
協働に行政の力は外せないと思い、渋谷区役所の防災課に「災害をテーマに一緒にやりませんか?」と言いましたら、「是非やりましょう」と快く受けていただきました。NPO法人にもご挨拶に行ったところ、協働の話が進みました。
他の地域でも災害をテーマにした取り組みをされていますので参考にして、「防災のまち歩きを夏体験ボランティアプログラム」にしてみようと思いました。
三者で、どういうプロセスで企画を決めていったのですか?
まち歩きの企画に取り組むのが初めてで、どうしたらいいのかよくわからない状況でした。講座を実施するまでの期間は短かったのですが、打ち合わせを4、5回やりました。リアルに歩いて現場を確認したり、オンラインやテーブルを囲んで会議をしました。
まずは、渋谷区役所を起点に地域の中の社会資源をめぐるようなルートを考え、「ここは行った方がいいね」と見学ポイントを三者で出し合いました。
三者協働で良かった点は、お互いの仕事内容を知ることができたことです。行政には行政の役割、NPOにはNPOの役割、ボランティアセンターにはボランティアセンターの役割があります。災害時に必要なことを三者で役割分担しながら担うことができるかなど、顔を合わせて取り組むことで話すことができました。
一方で、お互いに知らないことが多すぎたことを改めて実感しました。だからこそ、一緒に講座を作る機会がもてたことは良かったです。
当日はどのように進めましたか?
役割分担を決めました。例えば、区役所の職員さんには、防災倉庫の扉を開けてもらい中を見せてもらったり、避難所や区の防災システムを案内していただきました。私たちボランティアセンターは、全体的なコーディネートを行いました。
NPOは渋谷に拠点を置くADRA Japan(アドラ・ジャパン)という団体で、途上国の開発支援や災害被災地での緊急支援活動を行なっており、活動概要や被災地で実際にどんな活動をしているかを紹介いただきました。
参加者は初年度約20名で、学生が多かったです。まち歩きの後、実際に何か活動してみたいという高校生や大学生がいて、災害ボランティアに登録する人や、アドラ・ジャパンの活動が気になる人もいて、参加者には三者それぞれを知ってもらえる、広がりがある内容になったと思います。
協働する上で難しかったことは?
苦労したことは無かったです。
防災課も多岐に渡ったいろんな仕事をしているなあ、NPOも災害だけではなくて国際的な視点を持って活動しているなあ、と知ることができたのは大きな収穫です。1つの団体で取り組んだ方が意思決定は速いでしょうが、区役所とNPOと一緒に組んだ方が広がりを感じます。
また、それぞれに力があるので、私たちだけでは小さな力でも、一つ二つ違う団体と一緒に考えると、大きな活動になるのがいいですね。
単発で終わらずに、今でも三者協働がつながっているのは、お互いの役割が違うことがわかったからかもしれません。
三者協働をしてみたからこそ感じる、ボラセンの存在意義はありますか?
すごく難しいですね。ボランティアセンターとか市民活動センターと言われると、それに特化した活動と見られがちなのですが、実は、企業や学校、行政やNPOという、幅広い人たちとつながりを持って、うまく行くかどうかはわからないけどやってみませんかというきっかけづくり、社会参加を促す役割だと思います。それをどうやって見せて行くかが課題です。
社会福祉協議会の内部でも「ボランティアセンターはボランティアのことだけやっているんでしょ?」と思われがちなのですが、「いや、そうじゃないんですよ」を分かってもらうのに苦労しています(笑)。
企業や学校、行政やNPOの皆さんから、「何かやってみたい」と相談をいただくということは、そこにニーズがあるということで、「せっかくなら何かやってみましょう」と言うのが私たちの役割だと思っています。
渋谷区内でのボランティア・市民活動の推進を、今後どうしていきたいですか?
ボランティアセンターは「ボランティアの推進」が大切な取り組みの1つです。また、団体の支援や団体の連携の促進も求められています。今までの福祉というカテゴリーにプラスしていろいろなニーズがあるので、それを上手く連携をさせてプログラム展開していくのがセンターの課題だと思っています。
「地域における共生社会の実現」が最終ミッションですので、それに近づけるように、まだまだ知らない団体が多くあるので、そういう団体の皆さんと連携を図っていきたいです。
具体的には、子どもテーブルや子ども食堂と呼ばれる団体が200超ありますが、まだお近づきになってないところがあります。また、地域には草の根で活動している団体もたくさんありますので、地域福祉コーディネーターとも連携を図り情報をもらいながら、しぶやボランティアセンターと何かコミットできませんかと働きかけていきたいです。
広がりについては、行政区を超えて取り組んだこともあります。災害ボランティアセンターの設置運営訓練の時に、隣の区で何かあったらどうするのだろうと区境が気になっていたので、お隣のボラセンに声をかけました。行政職員の皆さんも、自分たちだけでやると思い込んでいたものが、お隣の自治体と連携を図る大切さを知るきっかけになったようです。区境を越える取り組みもやっていきたいです。
池畑さんの仕事に対する思いを教えてください
今、ボラセンのメンバーは3人なのですが、何でも言い合える関係、ちょっと気になったことを朝に昼に夕方に共有するようにしています。何でも言い合える関係になると、仕事がしやすいです。
相談を受ける時は、その人が何をやりたいかは、話の中にキーワードが出てくるので、そのキーワードに近いことでできることは何かなと考えるようにしています。「こういうプランでどうですか」と聞いて、相手が「ああいいですね」って乗ってきたら「ああ合ってたんだ」みたいな、会話をしながら形にしていく感じです。
つながるチャンスは、多分いっぱいあります。電話や窓口に来てもらうのは、すごいチャンスです。窓口だったら名刺を渡すチャンスがあるので、名前憶えておいてもらう。その後時間が経ってしまっても自分がつながりたいなと思った時に、「この間、お会いしました。こういうプログラムを一緒にやりませんか?」と提案するのも良いと思います。やりたいなと思うこと、形にしていくことを、常に考えておくことです。
先ずは声をかけて、知ってもらって、一緒にやりませんかと動機付けしてやってみて、楽しかったら次こういうのはどうですかとプランを提案していく。上手く行けばどんどん輪が広がって、知らない団体とももっと連携できるようになって行くと思います。