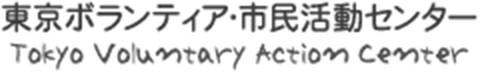狛江市市民活動センターこまえくぼインタビュー
「狛江市市民活動センターこまえくぼ」とは
「狛江市市民活動センターこまえくぼ」は、「市民と行政による参加と協働のまちづくり」という条例のもとに2016年に設置された狛江市の施設で、指定管理者として狛江市社会福祉協議会が運営しています。ボランティアや市民活動をしている方だけでなく、事業所や企業などと協働しながら狛江市のまちをよくする活動に取り組んでいます。
協働のまちづくりに取り組む中で、どんなつながりができましたか?
福祉分野以外の一般企業の方、福祉に関わらない活動をされている方々ともつながりました。
1つのきっかけは、狛江市内にコミュニティFMが開局し、こまえくぼに出演依頼があったことです。こまえくぼだけの出演ではもったいない、市民団体も紹介できないかと相談しました。なぜかと言いますと、コロナ禍を経ていろいろ状況が変わっていく中で、各団体にも自分たちの活動を見直してほしいと思っていたところだったのです。ラジオで自分の活動について語るとなると、活動を始めた思いや成り立ちなどを関係者でもう一度話し合って共有したり、自分たちの言葉で話したりことで、活動を見直すきっかけになるのではと考えました。ラジオの出演は現在も続いていて、こまえくぼも月1回出ています。先日、あるイベントを行なっている時に、「ラジオ聞いています」と参加者から声をかけられてドキッとしました。聞いていただいているのは本当に嬉しいことですが、下手なこと言えないなと思ったり。
また、ラジオのディレクターから吉本の芸人さんをご紹介いただき、こまえくぼのボランティアの基本を伝える動画に出演してもらったこともあります。社会福祉協議会はその名の通り福祉の団体で、福祉以外の関係者、特に芸人さんとつながることなどこれまでありませんでしたが、ラジオ出演を機に、思いもよらない新たなつながりができました。
コロナ禍での新たなチャレンジはありますか?
ラジオの出演以外にも、コロナ禍で取り組んだことがあります。
コロナ禍以前、小学校の授業で車いす体験やアイマスク体験を行っていました。コロナ禍で体験活動は中止せざるを得なかったのですが、児童たちにこの教育が全く抜けてしまうことが課題だと、これまで関わってきた市民のみなさんは感じていました。こまえくぼには、市民で活動する「部会」がいくつかありますが、その中の「体験学習部会」で「何とかできないか。動画を作って見てもらうのはどうか」という提案がありました。以前も多摩川の水害に関して体験者が語る動画を作製し、学校の授業の教材として活用してもらったことがあったのです。
「ぜひ動画を作製してみましょう」と言ったものの、大きな課題がありました。こまえくぼは、学校とのつながりがなかったのです。「学校の授業で動画を使ってもらえれば」と我々が考えても、学校ではどのような内容を求めているのかがわかりませんでした。どうしたらいいかと考えていたところ、退職された校長先生が集う会が市内にあるという情報を得て、ご相談できる方につながることができ、学校側の視点などをアドバイスいただきました。
この動画は、当初、体験ができないコロナ禍で活用することを考えていましたが、状況が少し落ち着いてきて体験活動が再開されていく中で、逆に「動画をどうしたらいいか、活かす方法はないか」という課題も出てきました。ある時、動画を見てもらってから体験をしたところ、子どもたちからの感想が多いと感じ、もしかしたらより理解が深まっているのではないかとの感触がありました。そこで現在は、動画を見てから体験学習をする流れになり、コロナ禍後も動画が活用されています。
体験学習部会の活動は、どうやってできていったのですか?
狛江社会福祉協議会で主催した「福祉カレッジ」では、講座終了時に地域の課題について考えるのですが、受講生のお一人が「障害がある方も地域の中で生活をしているのに、障害者について知らない人が多い。障害者に対する理解が進んでいない」という疑問を感じられたのが始まりです。その疑問をどうしたらいいかと相談を受け、まずは知ってもらう取り組みとして、障害のある方もない方もみんなが描いた作品を展示するアート活動をしようということになりました。当初はお一人の考えでしたので、一緒に取り組む仲間が必要だと少しずつ輪を広げていってもらいました。何人か賛同者ができましたが、いきなり展示場を借りたりするのは難しいので、こまえくぼのフリースペースを活用して展示会を行いました。
展示会をやってみながら、今後どうしていこうかと話し合い、活動が展開していった経緯があります。
こまえくぼが、市民参加や地域課題への取り組みで大切にしていることは?
地域課題について、市民のみなさんに伝える工夫をしていますし、それを知った方が「何か活動してみたい」という思いにつながっていくことをめざしています。また、こまえくぼが気付いていない課題を感じてご相談に来られた方がいらした時も、その思いが活動につながっていくようにしています。
地域の人たち、市民の人たちが主役で、その方々からの相談や思いが活動として展開するようにつないでいくことを大切にしています。
体験学習部会のはじまりでもお話ししましたが、こまえくぼを活用してまず展示会をやってみて、みなさんに見ていただき、今後どうしたらいいかを話し合い、少しずつ活動を大きくしていき軌道に乗せて行くという手法をとりました。こまえくぼは、拠点機能としてフリースペースを持っていることが大きな特徴です。拠点機能としてのフリースペースは、時には人が集まっておしゃべりができる場であり、時には団体が活動について発信する場として活用される、市民協働を進める上で大切な場所だと思っています。この場所があるから、つながりができます。
大山さんの仕事に対する思いを教えてください。
私自身、やっぱり人が好きです。こまえくぼのスタッフもみんなそうかなと思います。人から相談を受けたり、つながりを求められることに対して応えたいと思うし、何かにつながった時はやりがいを感じます。
かつては社会福祉協議会で障害分野や高齢分野で、ホームヘルパーなどもしてきましたが、その時に一緒に働いていたヘルパーさんがこまえくぼに来て、「あなたがいるから、ちょっとボランティアやって行こうか」と活動に参加してくれたり、「こういう特技があるのだけれど、できることない?」などとお声がけいただくと、なんとかつながるようにと動きますし、つながったことで「ああ良かったわ」と言われると、こちらこそ「ああ良かった」と思います。やっぱり一番大事にしなきゃいけないのはつながりで、まわりまわっている感じがします。
今後の抱負を教えてください
こまえくぼがあったことで、今まで難しかった福祉以外の新しいつながりができました。しかし、まだまだ知らないつながりがあると思っています。今後も、市内の色々な活動につながったり、団体や学校とつながったりしていく橋渡しをしていきたいです。