※この情報の内容は受付を終了しています。連絡先など変更されている場合がありますのでご注意ください。
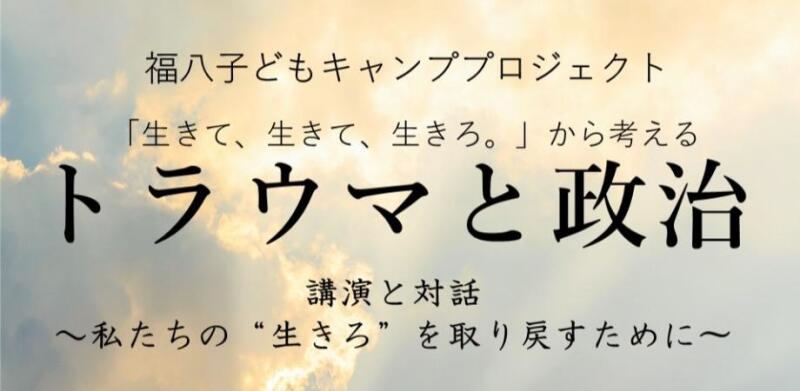
講演と対談
トラウマと政治 ー “声なき痛み”を語り始めるために
東日本大震災と原発事故。
映画『生きて、生きて、生きろ』は、PTSDや深い心の傷を丁寧に描くとともに、その背景にある政治的構造に鋭く迫りました。
震災で被災した人々のトラウマは、国家によって「もう終わったこと」として扱われ、その後の支援や記憶の継承さえも薄れていきました。さらに歴史をたどれば、原発政策そのものが、福島をはじめとする地域に“負担を強いる”ことを前提に成り立ってきた構造が見えてきます。
その構造は、日本を戦争へと向かわせ、戦地でトラウマを受けてきた人々の声を葬り去ってきた社会構造と全く変わっていません。
今回のイベントは、2024年に行った上映+対話会の“おかわり”企画として開催されます。
映画に出演した蟻塚先生、前回の対話会にも参加くださった中村先生をお迎えし、トラウマと政治について講演・対談、そして参加者の皆さんで対話会を行います。
蟻塚亮二(精神科医)
弘前大学医学部卒業後、精神科医として勤務。1985年から1997年にかけて青森県弘前市の藤代健生病院院長。その後2004年から2013年まで沖縄県那覇市の沖縄協同病院などに勤務。2013年から福島県相馬市の「メンタルクリニックなごみ」院長を務めるかたわら、現在でも月に1回沖縄での診療を続けている。著書に「うつ病を体験した精神科医の処方せん」(大月書店,2005)「統合失調症とのつきあい方」(大月書店,2007)「沖縄戦と心の傷 トラウマ診療の現場から」(大月書店,2014)(沖縄タイムス出版文化賞2015受賞),「悲しむことは生きること〜原発事故とPDSD」(風媒社,2023)など。
中村江里(上智大学文学部史学科准教授)
一橋大学大学院社会学研究博士後期課程修了、社会学博士。日本学術振興会特別研究員、広島大学准教授を経て、現在上智大学文学部史学科准教授。著書に「戦争とトラウマ〜不可視化された日本兵の精神神経症」(吉川弘文館,2018),「精神科診療録を用いた歴史研究の可能性と課題ー戦時下の陸軍病院・傷痍軍人療養所における日誌の分析を中心にー」(田中祐介編「日記文化から近代日本を問う」笠間書院、2017),「戦争と文化的トラウマ〜日本における第二次世界大戦の長期的影響」(共編者,日本評論社,2023)
2025年7月19日(土)
14:00~17:30
渋谷区
初台区民会館
渋谷区初台 1-33-10
https://traumaandseiji20250719.peatix.com/
peatixからお申込み下さい
定員になり次第締切とさせていただきます
なぜ“対話”の場を開くのか?話さなくてもいい。ただ、感じたことに言葉にしてみる。
「講演は聴きたいけど、“対話”は少し気が重い…」そんなふうに感じる方もいるかもしれません。
この場は、発言を強いるものではありません。話したくなければ、聴くだけの参加も歓迎です。講演を聴いてみる、隣の人の声を聴いてみる。自身の心の声を聴いてみる、そのとき、もし、それを言葉にしたくなったら、隣の人に話してみる、会場の皆に話してみる。そして、ある人にとっては、自身の心の声が言葉になるのを温める時間になるかもしれません。
“対話”と聞くと構えてしまうかもしれませんが、ここで行いたいのは「自分の感じたことを、少しだけ言葉にしてみること」、そして「他者の声に耳を傾けること」。
震災、原発事故、国家政策…私たちは「ただ従う」ことに慣れすぎていなかったか?
「なにかおかしい」と感じた心の声を、無意識に脇に押しやっていなかったか?
この場は、こころが感じた”何か"に耳を澄ませる時間です。
サンクチュアリとしての場をひらく言葉にできない痛みを抱えて、ここにともにいる。
日本社会にはまだ少ない「アジール(避難所)/サンクチュアリ(安らぎの場)」——
自分の感じたことを表明してもよい、安全な場所。
映画の中で「なごみ」は、まさに「アジール」として存在していました。こうした場を広げていくことこそが、
「トラウマを生み出す政治」や「痛みに目を向けない社会」に対して、
新たな仕組みを育む最初の一歩になると信じています。
私たちは、そんな思いや願いを込めて、この会を企画しました。
若者たちの声を、消さないために
「本当は、ずっと『なにかおかしい』と感じていた。けれど、言えなかった」
映画上映と対話会を経て、若い世代からそんな声が届きました。
「誰かを傷つけるんじゃないかと怖かった」
「政治の話なんて、してはいけないと思っていた」
今だからこそ、こころの声を少しずつでも言葉にしていくことができたら。それを誰かに伝えられたら・・・
この場は、そんなあなたの声を歓迎し、支え合う場です。
参加費の設定について
080-5379-0288
nobi.nasakejima@gmail.com(事務局 村上)