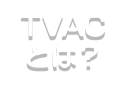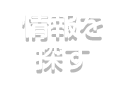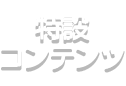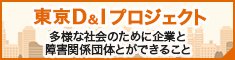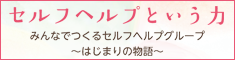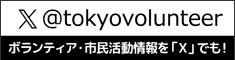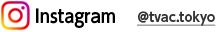(2013年3月6日 / TVAC )
帰ってきた! インターンのぼらせん奮闘日記
- キーワード
- 日本社会事業大学 、 インターン 、 ボランタリーフォーラム
連載その8(最終回) 平成25年3月6日(水) 「インターン無事終了! ありがとうございました!」
 フォーラム終了直後、実行委員長の鹿住さんと
フォーラム終了直後、実行委員長の鹿住さんと「市民社会がつくる ボランタリーフォーラム2013」が無事に閉会し、市民の熱意は冷めることなく更に高まって日々が続いていくなかで、この「帰ってきた! インターンのぼらせん奮闘日記」は最後の回を迎えました。
「見たよ!」という一言に欣喜雀躍し、この日記を思考錯誤しながらまとめて、形にすることができました。
皆さまに支えられながらこうして活動が続けられたのだと思います。
本当にありがとうございました。
私のインターンは今回をもって終わりますが、
いつかまた、インターンの方が新しい形で続けてくださると感じています。
閲覧いただき、ありがとうございました!
最終回終わり。
連載その7 平成25年2月27日(水) 「ボランタリーフォーラム終了!その2」
 スタッフの笑顔が弾けます!
スタッフの笑顔が弾けます!今回初参加した「市民社会をつくる ボランタリーフォーラム2013」。
当日の様子から私が考える「ボランタリーフォーラム」を参加するにあたってオススメしたい3ヶ条を誠に勝手ながら提案させていただきます!
(1)「善は急げ!」お申し込みはお早めに。
分科会によっては定員に達するためにお申し込みが終了するところもあります。お申し込みの受付は12月頃からスタートしているため、その時期になりましたらHPや掲示、チラシをチェックされるといいかと思いました。あわせて、何の分科会をお申し込みしたかをメモしておくと当日の移動がスムーズに進みます。
(2)「急がば回れ!」階段も利用して会場移動。
分科会の会場がいくつかに分かれているため、開催会場の中心となる飯田橋セントラルプラザで10階と12階の部屋を利用しています。エレベーターを使用すると10階〜12階まではエレベーターの乗り換えが必要です。ボランタリーフォーラム開催中は非常階段を特別に使用しての移動が可能となります。2階分、されど2階。移動を効率化、節電、運動不足の解消、普段は入れない場所へのワクワク感……等理由はさまざまかと思いますが、オススメします。
しかし、焦らず、慌てず、落ち着いて。
階段で転んで怪我をなさいませんよう、昇降を譲り合って利用ください。(つまずくとやはり痛いです。)
(3)「早起きは三文の得!」フォーラムは最初から最後まで。
早い時間では9時から開催されたボランタリーフォーラム2013。遠方にお住まいの方や時間によって用事等があり、全日程の参加はなかなか難しいかもしれません。今回はカテゴリーごとに継続性をもって行われた分科会もありました。ひとつの分科会だけではなく、続けて参加することによってストーリー性をもって感じられるものがあります。
また、参加費以上にしっかりと得て帰っていただけると嬉しいです。もちろん、「この分科会の内容を聞きたいために参加した!」という方もいらっしゃると思います。その方も、他の分科会に参加申込状況を確認して飛び入りで参加されてみたり、展示物やCafeスペースを利用していただけたらと思います。
いかがでしょうか。参加された方から見て、うなずきたくなるような内容となっているでしょうか。ぜひ、この3つを来年の「市民社会をつくる ボランタリーフォーラム2014」で実践していただけたらと思います!
第7回終わり。
連載その6 平成25年2月15日(金) 「ボランタリーフォーラム終了!」
2013年2月8日から2月10日にかけて「市民社会をつくる ボランタリーフォーラム 2013」が皆さまのご協力のもと開催されました! 天候にも大変恵まれて、約1,200名もの方々に参加していただき、無事に終えられたことを嬉しく思います。
 がんばるぞー、おー!
がんばるぞー、おー!この3日間は開始前に必ず実行委員・サポーターのミーティングが行われ、 注意事項や申し込み人数や参加者人数を確認。その最後には鹿住実行委員長のあいさつがありました。
2月8日は、「これだけ人が集まれば、今までの(9)苦労も(9)苦にならない!」
これまでの日々を振り返りながら初日にかける思いを強く感じました。
この鹿住実行委員長の掛け声は「ボランタリーフォーラム」では恒例のものとして行われているそうです。 今年は「ボランタリーフォーラム」が第9回目になるため、「9」にちなんだありがたいお言葉が3日間聞くことができました。「うっ、うまい……!」と聞きながらうねったお言葉の数々です。
それが、こちら。
2月9日「(9)急なトラブルが起こるかもしれませんが、(99)汲々とせずがんばろう!」
焦らず、慌てず、落ち着いて。そんなメッセージを感じる一言です。
2月10日「延べ900人の参加者が、休(9)日にも関わらず参加してくださいます。探究(9)心をもって、多くのことを吸(9)収してもらえるように、わたしたちも追求(9)していきましょう!」
最終日として1番「9」が多く使われています。 これまでの積み重ねとこれからの意気込みを奮い立たせるような言葉ですね。
この3日間をこちらの言葉で始まり、37分科会が実施されました。参加者の皆さまには、学齢期前のお子さんから学生、社会人、ご年配の方々まで幅広い年齢層の参加があり、あの会場がひとつの地域社会として形成されていたと思います。そして、今回のテーマである「試される市民力(わたしたちのちから)」を私自身振り返りながら、何が今試されているのか、市民力とはなにかを学び、考える機会となりました。
7月の実行委員会からボランタリーフォーラムのサポーターとして参加させていただき、会を重ねるごとにその中身が創られていくのを感じながら、 当日を迎えるのがとても待ち遠しくなっていきました。こうして、学生ながら貴重な機会を得て、参加できたことに深く感謝しております。
ありがとうございました。
最後に、Facebookにて「市民社会をつくる ボランタリーフォーラム2013」のページがございます。
https://www.facebook.com/ShiMinShakaiwotsukuruvoluntaryforamtokyo2013
委員会の様子や開催期間中の様子が掲載されていますので、ぜひご確認ください!
では、終わりの言葉を「9」にちなんで。
「探求(9)心をもって、苦(9)ではなく幸福(9)を築いていく市民力(わたしたちのちから)」
第6回終わり。
連載その5 平成25年2月8日(金) 「ボランタリーフォーラム開催!」
ついに、今日から三日間にわたって待ちに待った「ボランタリーフォーラムTOKYO 2013」が開催されます!
7月から委員会に参加させていただき、ひとつひとつ築かれていく様子を感じてきました。委員会メンバーの方々がそれぞれに思いが込められた4つのカテゴリー「つながり」「生活・くらし」 「若者の市民力」「ボランタリズム」そして、それぞれのカテゴリーごとに3日間で37分科会が開催されます。
私自身、初参加となる今回のボランタリーフォーラムをとても楽しみにしています。テーマの「試される市民力(わたし たちのちから)」をどのように皆さんが考えられているか、一緒に考えさせていただけたらと思います。
お天気は心配していた雪マークもなく、晴れの日が続きそうです。皆さんの参加を心からお待ちしております!
第5回終わり。
連載その4 平成24年12月26日(水) 「ボランタリーフォーラム実行委員長へのインタビュー」
日本各地できれいな雪化粧が見られる季節になりました。
秋から冬にかけて期間があいてしまいましたが、4回目となる今回は「ボランタリーフォーラム2013」の実行委員長である鹿住貴之さん(認定NPO法人JUON(樹恩) NETWORK事務局長)にボランタリーフォーラムに対する思いを伺いました。
実行委員長として毎回の実行委員会の調整や取りまとめをされる姿から、このボランタリーフォーラムへの熱い気持ちをひしひしと伝わってきます。今回あらためてお話を伺い、その思いがつまった「ボランタリーフォーラム2013」の開催が私としてもとても待ち遠しく感じました。
大変お忙しいなか、ご協力いただきありがとうございました。
第4回おわり。
連載その3 平成24年9月26日(水) 第3回「ボランタリーフォーラム実行委員会」
 実行委員会のグループディスカッションのようす
実行委員会のグループディスカッションのようすすっかりと秋めいたこの頃。さっそく旬の秋刀魚をおいしくいただきました。「食欲の秋」の始まりです。皆さんは「○○の秋」と聞かれると何をイメージするでしょうか。
第3回目となる今回は、「市民社会がつくるボランタリーフォーラムTOKYO2013」
に向けた実行委員会の様子をお伝えしたいと思います。
今年はわたしたち市民の力が試されている!
まだ詳しい内容は非公開となっていますが、東日本大震災、原発事故を契機に「価値観」がどのようにかわってきたかを皆さんで話し合いたいと思います。
この記事があげられた今日(9月26日)、この実行委員会が開催されます。各分野で活動されている皆さんが集まり、その思いをどのように形づくられていくのかを委員会の様子を知ることを通じて一緒に感じていただけたら幸いです。
脂がのった秋刀魚が私たちの手に届くまでにたくさんの人の存在があるように、ボランタリーフォーラムもたくさんの人たちの手によって支えられています。次回はこの実行委員会のメンバーの皆さんについてお伝えしたいと思います。
第3回 おわり。
連載その2 平成24年8月21日(火) 第2回「ボランタリーフォーラムとは」
こんにちは!
オリンピックへの熱が冷めやまないですが、同じように冷めることがない私たちの市民活動に対する熱意は続いています。そんな第2回目は「ボランタリーフォーラムについて」。私はインターンシップを申し込んだ際にその名前を聞くまで、実はそういったイベントが開催されていることを知りませんでした。そんなボランタリーフォーラム初心者な私は職員さんからのお話やHPをみて勉強しました。
こうしたボランティアの啓発普及やボランタリズムを考える内容のイベントを、こちらのTVACでは継続して行われてきました。1984(昭和59)年から開始した「とうきょうボランティアまつり」では、ボランティア活動を「楽しむ」ことを前面に押し出された「まつり」を開催。ボランティア活動に対する関心や興味を持つ人が増え、全国各地で行われる同じようなイベントの先駆けを担いました。
1992(平成4)年には「ぼらんてぃあ・めっせ・東京」とリニューアルされました。それは、ボランティア活動の場や活動者層が広がるにつれ、課題の整理・追求やネットワークの拡大、新しい活動の展開を生み出す啓発と提言を行うことを目指したものでした。
28年の市民によるボランティア活動の歴史がこのイベントにはあるのです。「いくわよー!(1984)」で始まった市民活動を盛り上げるイベントは、ボランティア活動や市民社会づくりを活性化させる力と楽しさがあります。(学校のテストには出ないかもしれないけれど、覚えておくとお得です!)
東京を中心に全国で市民社会をつくる市民が集まり、現代の社会状況に目を向けて、よりよい社会が市民の手によってつくりだされていくためにはどうしたらいいのでしょうか。きっかけは一人ひとりの思いからかもしれませんが、思いを共にする人々が集まることで今ある社会を変える大きな力が生まれていきます。
千里の道も一歩から。
私たちの社会活動を支える市民社会の歴史を感じました。
とても素敵なイベントの運営に2012年度はインターンシップとして参加できることをとても嬉しく思います。本番に向けて既に2回ほど実行委員会が開かれています。次回はまさしく市民の手でよりよい社会を築かれている方々が参加されている実行委員会の会議の様子を報告します!
第2回おわり。
連載その1 平成24年8月10日(金) 第1回「はじめてのTVAC」
東京ボランティア・市民活動センター(TVAC)で平成24年7月24日〜平成252月10日までインターンシップでお世話になることになりました。日本社会事業大学3年の鈴木理紗です。主にボランタリーフォーラム実行委員会と情報発信を担当し、これから約8ヶ月の間、インターンシップを通して学んだことや感じたことをちょこちょことお伝えしていきたいと思います。
 入り口から見た事務スペース。オリジナルののれんがかかっています。
入り口から見た事務スペース。オリジナルののれんがかかっています。第1回目となる今回。私は8月5日から10日にかけてセントラルプラザ10階のTVCAの窓口受付をこえて職員の皆さんのなかに入り、業務を教えていただきました。机の位置が変わる「フリーアドレス」制を取り入れられていて、日によって働く場所(机)が異なるそうです。その日によって場所が変わるのは見える世界も変わり、気分転換にも繋がっていいですね! そして、皆さんの机は毎日片づけられているのでとてもきれいです!
この5日間はウェブサイトの情報発信と社会福祉協議会やNPO法人等から送られてきたニュースレターの整理を主に行いました。TVACのウェブサイト「ボラ市民ウェブ」は毎日たくさんの情報が寄せられており、その内容が更新されています。初めてHPを拝見させていただいたときには、情報の多さと更新スピードの速さに驚きました。その作成がどのように行われているか、インターンシップで解明したい謎の一つでもありました。その答えはHP作成の腕前の高さとTVACが東京の中間支援組織としての役割を中心に担っているからなのだと考えます。このHPは見た人が惹きこまれるようなボランティア情報やNPO法人の紹介、地域情報が盛り込まれています。それらをさらに惹き立てる職員の皆さんの文章が綴られています。そして、多くの情報が寄せられるということは存在感や信頼が集まっている所であると感じます。職員の皆さんの業務に対する関わり方や姿勢がその運営やHPの内容にも繋がっているのだと思いました。
ニュースレターは社会福祉協議会やNPO法人等の活動報告や思いが一枚(一冊)にまとめられています。たくさんの団体があることに驚く(NPO法人は都内に約9000あるそうです!)とともに、活動の内容にとても興味を抱きました。住民同士の安心な環境づくりを行う団体や日本各地で生活する人々に関わる団体、海外の暮らしに関わる団体、等などその団体の活動から参加している人々の思いが伝わってきます。整理しながらニュースレターを読み込む…家の片づけをしながらマンガを読んでしまうようなとても素敵な時間です。ボランティア保険の登録などで来所された際には、ぜひニュースレターを手にとってゆっくりご覧ください。ちょっとした一息に、東京ボランティア・市民活動センターで限定販売されているおいしい「ぼらせん」もオススメです!
 「ぼらせん」は定番のしょうゆ味ほか全5種類。
「ぼらせん」は定番のしょうゆ味ほか全5種類。「ぼらせん」と書かれたのれんと温かい職員の皆さんに迎えられて、TVACに訪れた方は次のボランティア活動や組織活動を行う力が沸き上がってくるかと思います。短い期間ではありましたがセンター業務に関わらせていただき、知らなかった世界をたくさん学んだ5日間でした。これから学生として多くのことをより学んで深めていきたいと思うとともに、熱い思いを抱えて社会福祉のお仕事をされている皆さんの姿勢を目指していきたいです。この文章を通して少しでもその成長を感じていただけると幸いです。
第1回おわり。