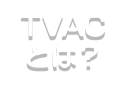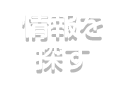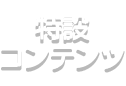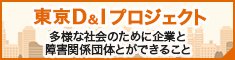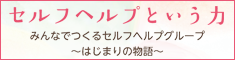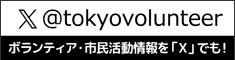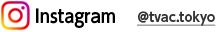TVACのあゆみ
~東京におけるボランティア活動支援の流れ~
第2章 東京都ボランティア・コーナーの設立
 コーナー発行の「ボランティア手引」では、
コーナー発行の「ボランティア手引」では、1974(昭和49)年の発行以来、数多くの
ボランティア活動が取り上げられた。
1969(昭和44)年に出された東京都社会福祉審議会から「東京都におけるコミュニティ・ケアの進展について」の答申が行われ、従来の施設を中心とする限定された対象への福祉サービスから、地域社会において必要な者が誰でも利用できるコミュニティ・ケアヘの発展が提言された。以来、民生局(現在の福祉局)を中心に、コミュニティ・ケアを進めていくうえでのボランティア活動の位置づけとボランティア活動への行政の援助のあり方について検討が行われた。
そして、1971(昭和46)年にNHK論説委員であった縫田嘩子が東京都民生局長に就任すると、民生局婦人部をボランティアに関する所管部とし、積極的な調査研究を行った。縫田は「ボランティア活動は自発的な活動である。したがって、民間の自発的な活動であることが原則である」としながらも、「福祉行政の担当する責任者として、行政の中でボランティアの推進を唱えた。それは、日本におけるボランティア活動の発展を期待する一市民としての願いがあったからにほかならない」と定年後に書かれた回想録「福祉・人と心」のなかで述べている。縫田は福祉の発展のためには、その基盤としてのコミュ:ニティ、住民の支えがなければならないとした。
また、ボランティア活動への支援は、主婦たちの潜在的な能力を積極的に生かす婦人施策としても、民生局婦人部を中心に検討された。当時、ボランティア活動の主役は子育てをとおして地域社会とのかかわりを深めてきた女性たちであった。彼女たちは、母親として、学校や地域社会において子ども会活動や公民館活動等に積極的に参加していた。また、この時代は女性たちが社会参加を求めた時期でもあり、消費者活動、リサイクル活動、生協活動などが展開されていたという社会的背景があった。
しかし、こうした行政によるボランティア活動への支援については、疑問や反論も多くあり、4年間にわたる調査研究や関係者との話し合いなど、慎重な準備が行われることになった。
まず、1972(昭和47)年2月には、ボランティア活動の援助のあり方に関する局内関係課長によるプロジェクト・チームが設置され、以来9月までに11回開催される。最終回での報告では、コミュニティ作りを最終目標として、その人的側面を支えるものとしてボランティア活動を位置づけ、ボランティア供給的側面、受け入れ的側面、連絡調整的側面の3面の総合的条件整備を行政の課題とするとした。また、都内数か所の社会福祉協議会を拠点としたモデル地区を設定することや中央にボランティア・センターを設置し、全都の連絡調整とモデルとしての事業を行うことなどが盛り込まれた。なお、中央のボランティア・センターの運営に関しては、都で設置するが、条件が整い次第民間団体に移管することや、民間のボランティア関係団体の代表によりボランティア協議会(仮称)を設置し、モデル地区およびボランティア・センターの事業について助言勧告するとともに、団体相互の連絡調整にあたるとしており、「民間主導」の事業運営をすることがうたわれた。
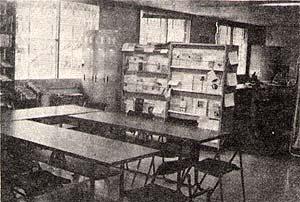 東京都ボランティア・コーナーの内部。コーナーは当初、
東京都ボランティア・コーナーの内部。コーナーは当初、渋谷区の東京都児童会館の一室に設置され、後に同区内の
美竹ビル(現・東京都防災・建築まちづくりセンター)に移転した。
また、同年6月には、民生局婦人部が吉澤英子ほか4氏に「婦人ボランティア活動の現状と課題」について研究委託した。吉澤ボランティア研究会では、8月に中間報告として「ボランティア援助事業についての基本構想」が提言され、翌年3月には最終報告を提出した。これらの報告書のなかで、ボランティア活動は主権在民の主体性を確立する憲法理念に基づくものであり、住民と共にする政治の実現をめざし、積極的に援助施策を行うべきであるとされた。また、ボランティア活動に対する住民・行政の理解不足や・民間推進団体の連携不足などの現状において、行政は将来の展望にむけて、連絡調整、情報、調査企画、教育訓練などの機能を持つボランティア・センターを設置し、民間の学識経験者や関係団体の代表による特別委員会によって運営すべきであるとした。さらに、今日の社会福祉協議会が再編強化されることにより、センターの役割を果たすことも可能だが、現状では分離し、提携を図ることが適当であると述べている。なお、当面、都内のボランティア活動が直面している無理解、資金不足、リーダー不足の3大問題に対処するため、都はボランティア・コーナーを設置すべきであり・コーナーは情報・宣伝・連絡調整、リーダー養成を行うほか、会合等の場や器材の提供や相談を行うこととした。
こうしたプロジェクトや研究会の報告を受け、東京都の1973(昭和48)年度予算において、ボランティア活動推進援助事業が認められることとなった。ボランティア活動推進援助事業の予算総額は390万円であり、事業項目は、①ボランティア関係団体等によるボランティア協議会を設置し、事業の運営についての助言を得るとともに、団体相互の連絡協議の場とする、②民間人による専門の相談員と事務職員を配置したボランティア・コーナーを設置し、相談助言に応じるとともに、情報資料、活動器材、会合の場を提供し、ボランティア活動の便宜を図る、③当面モデル地区は設定せず、今後の推移をみる、④事業の運営に当たっては、ボランティア関係団体の主導性を尊重し、状況の進展によっては民間団体に事業主体を移管し、都は施設、経費の援助のみにすることも展望する、とした。
さらに、4月7日には、吉澤ボランティア研究会の呼びかけで、ボランテイア関係団体による「東京都ボランティア活動育成機関連絡協議会」(以降、3回の名称変更を受けて、現在の東京都ボランティア活動推進協議会となる)が発足し、各団体の活動報告や問題提起とともに、協議会の役割やボランティア・コーナー構想について協議を重ねた。そして、7月には本協議会の検討内容を盛り込んだボランティア・コーナーの設置案が都より示され、協議会の了承を得ることになった。さらに、本協議会からボランティア・コーナーの運営委員を選出し、都が依頼した。そのなかには中島充洋(東社協事務局次長)、枝見静樹(富士福祉事業団理事長)、松本勉(日本YMCA同盟主事)、香山篤美(日本青年奉仕協会職員)らが含まれ、吉澤栄子他相談員およびコーナー担当員代表がコーナー開設の準備を行った。そして、長い協議の末、1973(昭和48)年の10月1日、都民の日に東京都ボランティア・コーナーが開設された。
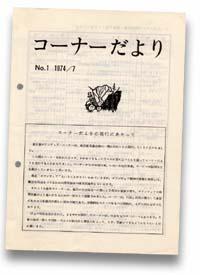 東京都ボランティア・コーナーが発行した
東京都ボランティア・コーナーが発行した「コーナーだより」。1974年7月創刊。
現在のボランティア・市民活動情報誌
『ネットワーク』の原型。
以上の経過からも推察されるとおり、東京都全域を対象としたボランティア活動の推進・支援拠点は、その設立および運営主体を行政としながらも、民間のボランティア関係者からなる運営委員会が決定権を持つとともに、民間の相談員を配置するといった「民間主導」で運営されており、現在に至るまでこの原則は引き継がれている。
東京都ボランティア・コーナーには専任の職員を配置せず、東京都社会事業学校の卒業生がつくる「泉の会」の有志がボランティアで業務を担当していた。また、運営には学識経験者、推進団体代表、東京都社会福祉協議会関係者、東京都担当職員によって構成される「運営委員会」があたった。そして、運営費用はすべて東京都の予算によって支弁された。
一方、東京都社会福祉協議会を中心に、区市町村社会福祉協議会がボランティア活動支援に本格的に取り組みを始めたのもこのころである。東京都社会福祉協議会では昭和49年に、ボランティア受け入れおよび活動状況調査を、翌年には社会福祉施設ボランティア活動受け入れ状況調査を実施するとともに、1975(昭和50)年より、都内3地区において移動ボランティアスクールを実施した。そして、1976(昭和51)年には、地区ボランティア活動推進事業をスタートさせた。さらに、1977(昭和52)年には厚生省の補助事業として「学童・生徒のボランティア活動普及事業」が全国の社会福祉協議会によって実施されることになった。1978(昭和53)年には都内のボランティア活動の実践団体・推進団体・助成・援助団体からなるボランティア団体連絡協議会を東京都社会福祉協議会内部の会員組織として発足している。以上のように、東京都社会福祉協議会は社会福祉分野を中心に、会員である社会福祉施設や区市町村社会福祉協議会あるいはそれ以外のボランティア関係団体をも会員としながら、それらとのネットワークのなかでボランティア活動を支援する体制を徐々に確立していった。ようやくボランティア活動への取り組みが活発化した区市町村社会福祉協議会は東京都社会福祉協議会に対して、活動事例やセンターの運営手引き、講師等の紹介など、情報提供機能を期待するとともに、現場担当者の研究教育機能等に期待していた。
このように、東京都におけるボランティア活動の推進は、東京都ボランティア・コーナーと東京都社会福祉協議会との2本建ですすめられることになった。