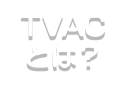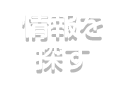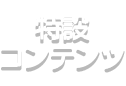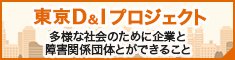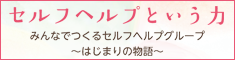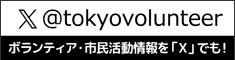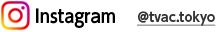TVACのあゆみ
~東京におけるボランティア活動支援の流れ~
第6章 東京ボランティア・市民活動センターとしての展開
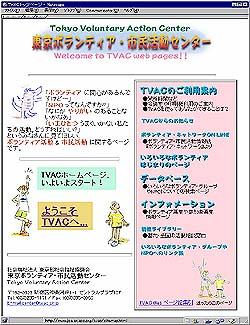 1998年11月に立ち上げた東京ボランティア・
1998年11月に立ち上げた東京ボランティア・市民活動センターのホームページ。(開設初期の画面)
東京ボランティア・市民活動センターは、東京都の懇談会や独自の委員会での協議をふまえ、従来のボランティア活動に加え、多様な市民活動を推進・支援することを目的としている。 センタースペースはセントラルプラザの7階から10階に移り、2倍に広くなったものの、予算や職員体制は変わらず、従来の事業をボランティアだけでなく市民活動団体をも対象とするように工夫しながら進めることとなった。 情報事業では、本センターに毎日集まる膨大な情報のデータベース化やインターネットの活用である。 1998(平成10)年11月に作成したホームページのなかには、市民活動団体データベースを作成し、その団体の活動状況や参加・協力の仕方が掲載されている。 また、市民活動のウィークリー情報が市民をはじめ、企業やマスコミ等にも活用されている。
相談事業では、法人格の申請やその後の運営、ボランティアの募集や広報協力依頼等、多様な相談に対応している。
調査研究事業としては、1999(平成11)年3月に都内を対象とし 「市民活動団体の実態およびニーズ調査」 を実施し、各団体の厳しい状況やセンターへの要望を把握した。
研修事業のなかでは、市民活動団体向けの法人格取得およびその後の経理、税務、労務等の実務研修を実施するとともに、米国大使館や海外の関係団体の協力を得ながら、組織運営に関する専門講座を開始した。
啓発事業では、 「ボランティアめっせ東京」 を 「めっせTOKYO」 と名称変更し、今まで以上に多様な市民活動者・団体、関係団体の参加を図っている。
災害事業では、東京都における災害ボランティア活動の支援拠点としての準備を進めている。 阪神・淡路大震災の際には、兵庫地区を中心としたボランティアの組織化や行政との連携に取り組むとともに、後方支援の拠点として、人材、資金、物資に関する情報をコーディネートしている。1995(平成7)年の7月には、東京都社会福祉協議会の災害対策委員会のなかで災害時のボランティア活動の支援を検討するとともに、センターの調査研究事業として、災害ボランティア活動支援システム研究委員会を設置し、全国および東京都全域、区市町村レベルでの災害ボランティア支援の仕組みを検討した。 一方、阪神・淡路大震災の際に活動した東京の市民活動団体が緩やかなネットワーク組織、「東京災害ボランティアネットワーク」をつくり、本センター内に事務局を置きながら、研修や訓練を行うとともに、水害や台湾地震等への支援活動を展開している。
 米国のNGO、ザ・ネイチャー・コンサーバンシーとの
米国のNGO、ザ・ネイチャー・コンサーバンシーとの『戦略的マネジメント研修』の様子。
近年では海外の団体との共同プログラムにも活発に取り組んでいる。
また、教育改革の大きな柱として、2002(平成14)年度からはじまる「総合的な学習の時間」の実施に向けて、民間助成財団からの助成を得ながら、英国の民間非営利団体であるコミュニティ・サービス・ボランティアズ(CSV)との共同研究事業を実施し、また、児童・生徒のボランティア活動普及事業のなかで、都内における研究協議会を開催し、参考資料を作成している。一方、2000(平成12)年から2001(平成13)年にかけて、米国のNGO、ザ・ネイチャー・コンサーバンシー(TNC)とNPO/NGOを対象とした「戦略的マネジメント研修」を実施し、NPO/NGOにおけるマネジメント能力の向上を目指したプロジェクトにも取り組んでいる。
なお、より利用しやすいセンターづくりをめざして、1999(平成11)年12月からは、閉館日を従来の日曜日から月曜日に変更するとともに、開所時間も平日の夜8時まで、土曜日の5時までを、平日および土曜日の夜9時まで、日曜日の5時までと延長した。 そして、2000(平成12)年度には、本センターを資金的に支援する 「サポーター制度」 を実施することになり、より多くの市民や関係者が利用し、支えるセンターづくりに取り組んでいる。
こうした東京ボランティア・市民活動センターの先駆的な事業は全国からも注目され、各種イベントには全国から参加を得ている。 東京ボランティア・市民活動センターは東京都をその支援エリアの中心としながらも、テーマに応じ関東地域あるいは全国、世界とのネットワークの中で事業を展開している。2001(平成13)年にはセンター設立20周年を迎え、ボランティア・市民活動の普及と理解、そして、NPOなどの非営利団体と企業、学校、行政の多様なセクターによる協働のしくみづくりを目指し、さらなる活動に取り込んでいる。
※文中敬称略。また役職等は当時。