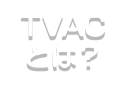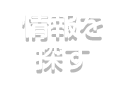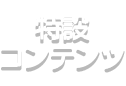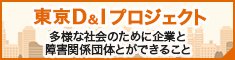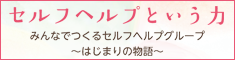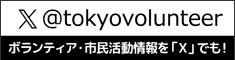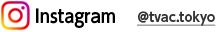TVACのあゆみ
~東京におけるボランティア活動支援の流れ~
第4章 東京ボランティア・センター事業の拡大と発展
 東京ボランティア・センター開設記念シンポジウムの
東京ボランティア・センター開設記念シンポジウムの様子(1981.5.30)
昭和56年には東京ボランティア・センターの最初の所長は東洋大学教授の吉澤英子が就任し、開所のつどいが開かれた。 また、青年ボランティアの体験学習の実施、都民ボランティアのつどいの開催、情報誌「ボランティア・ネットワーク」の発行、病院におけるボランティア受入調査研究(受入手引書の作成)および研修システムとボランティア変容課程調査研究の実施、ボランティア基金設立等各種事業が開始された。 最初の数年には、ボランティア活動と必要負担を研究する会の設置や児童養護施設におけるボランティア受け入れ調査、ボランティア活動推進のための地域氷解に関する研究委員会など、重要な調査研究が次々と行われた。 また、明日をつくるボランティアのつどいをはじめ、緑のまちづくりと公園ボランティア活動研修会や教育関係者ボランティア研修会など、福祉以外の分野をも対象としたつどいや研修が開催された。
昭和59年には、セントラルプラザ(東京都飯田橋庁舎)の新築に伴い、当時文京区茗荷谷にあった東京都社会福祉協議会の他の部署とともに、現在の場所へと移転することなった。 このことにより、以前より広いスペースが確保できるとともに、都内全域からのアクセスが容易になった。 新しいセンターの広報も兼ねて、第1回とうきようボランティアまつりがセントラルプラザにおいて盛大に開催された。 その後、東京ボランティア・センターは現在まで、まさに、首都圏および国際都市におけるボランティア・センターとしてその事業を拡大・発展させてきた。
 情報紙「ボランティア・ネット・ワーク」創刊号。1981年10月発行。発行当初から東京や国内、また海外のボランティア活動を積極的にとりあげていた。
情報紙「ボランティア・ネット・ワーク」創刊号。1981年10月発行。発行当初から東京や国内、また海外のボランティア活動を積極的にとりあげていた。(1) 情報事業
東京ボランティア・センターでは、ボランティア活動の推進に役立つようなあらゆる情報を収集、整理・加工し、ボランティア活動推進団体のみでなく、ボランティア活動に参加したい個人や学校、企業等の団体あるいはボランティアを受け入れる社会福祉施設や公共団体、マスコミ、研究者等幅広い関係者・団体に提供してきた。 発行物としては、月刊情報誌や研究年報、各種啓発資料、そして、ボランティア担当者向けの資料集「ボランティア活動便利帳」などがあげられ、設立当初から海外情報担当の専門員を配置し、その収集・活用を図っていることも本センターの特徴であるといってよい。
平成8年からは電子情報の専門員を配置し、データーベースの構築を開始した。
(2) 相談事業
相談事業も情報事業と同様に幅広い関係者や一般市民を対象に行われている。 ボランティア活動をこれから始めたい個人あるいは団体から、また、ボランティア活動の実践者・団体より活動を進めるうえでのさまざまな相談が日常的に入ってくるが、これらに対して、それぞれのケースにあった相談を職員全員が対応している。 特に、相談の最初の段階と相談情報の整理、相談記録の処理を行う専門員を平成7年から配置した。
(3) 研修事業
センターの設立当初から昭和60年度までは、(1)ボランティア活動推進団体職員、(2)社会福祉施設のボランティア受け入れ担当者、(3)学校のボランティア活動担当教職員、という3者を対象とした研修と課題別研修を実施してきた。 その後、ふえつづける区市町村社会福祉協議会のボランティア担当者のために、ボランティア活動推進団体職員の研修を新任研修、一般研修、専門研修と段階別に実施している。 そして、それまで必要に応じてテーマ設定されていた研修を「ボランティア・コーディネーター研修体系」として平成6年・7年度に体系化を試みた。
(4) 調査・研究事業
東京ボランティア・センターでは、毎年、ボランティア活動の推進にかかわる実態や諸課題について調査・研究を行うとともに、ボランティア活動推進の基本的な方向性を研究し、各方面に大きな影響を与えてきた。
昭和50年代後半になると、ボランティア活動が活発化するにつれ、ボランティアについての考え方が多様化するとともに、有償の在宅福祉サービスが広がっていくなかで、「有償ボランティア」という言葉が生まれた。 これに対し、センターでは昭和57・58年度に「ボランティア活動と費用負担に関する調査研究」を実施し、ボランティア活動の無償の範囲を検討するとともに、昭和61年・62年度には「今日的状況下におけるボランティア活動に関する問題研究委員会jを発足させ、社会動向やボランティア活動の状況分析をしたうえで、課題整理やこれからのあり方を提言している。
(5) 啓発事業
啓発活動は東京ボランティア・センターが昭和59年に飯田橋に移転したのを契機に始まった。 「とうきょうボランティアまつり」という名称をつけ、ボランティアの参加・協力を得ながら、一般市民への啓発キャンペーンとして記念講演やシンポジウム、また、ボランティア・グループの交流会が行われた。 翌年からは、障害者への理解を深めてもらうために「車いすミニマラソン」を実施し、子どもたちの参加を求めた「ボランティア王国をつくろうよ」も始まった。 昭和62年度からは、ボランティア活動ミニ体験を19種類にまで拡大して実施した。 こうしたまつり形式が区市町村レベルあるいは他県にも波及したことから、平成5年度より、ボランティア活動関係者が分野ごとの壁をやぶって、共通テーマで研究協議する「ボランティアめっせ東京」が開催されるようになった。
(6) 地区ボランティア活動推進事業
昭和48年度に厚生省が「社会奉仕活動センター事業」を開始したが、その動きにあわせて東京都では昭和51年度より「地区ボランティア活動推進事業」を開始した。 これは、区市町村をモデル地区として指定するもので、このことによりほとんどの社会福祉協議会がボランティア活動の推進に取り組むようになった。 そして、指定地区の連絡会が年数回開催され、情報交換や協働研究が行われてきた。 本事業は昭和63年度の指定をもって終了し、昭和60年国庫補助として開始された「福祉ボランティアの町づくり事業(ボラントピア事業)」の拡大へと発展的に解消されていった。 ボラントピア事業は区市町村社会福祉協議会に対して2年間にわたり年600万円の事業費を補助したが、東京都ではさらに400万円をコーディネーター人件費として上乗せした。 各区市町村社会福祉協議会はこうした事業をとおして、人的体制を確保し、ボランティア活動への支援を積極的に展開した。
こうした資金的なバックボーンにより、区市町村社会福祉協議会にボランティア・センターが誕生し、専任スタッフや管理職を配置していった。 そこで、平成3年度より、ボランティア・センター長会議を年数回実施することになった。
(7) 児童・生徒のボランティア活動普及事業
本事業は、都内の学校を協力校として3年間指定し、毎年10万円の助成金を提供しながら、各学校においてボランティア活動に取り組むことを社会福祉協議会が支援するというものである。 まず、昭和52年度に「学童・生徒のボランティア活動普及事業」という名称で全国的に始まり、その後、昭和59年度に東京都が指定枠を拡大し、「児童・生徒のボランティア活動普及事業」と名称変更した。 東京都においてはその指定枠が拡大し続け、平成2年度には300校以上の枠が予算化された。 学校教育関係者のボランティア活動への関心の高まりもあり、指定校数は飛躍的に伸びていった。 また、平成元年度から、指定を終了した学校のなかから各地区1校に限り「推進モデル校」として指定することが可能となった。
(8) 青年ボランティア活動推進事業
本事業は青少年(おおむね15歳~30歳)を対象とし、東京都の補助事業として昭和55年度に開始された。 その内容としては夏休みのボランティア活動体験学習と青年ボランティアのつどい、および映画の作成が毎年行われてきた。
当初、体験学習は本センターの単独実施でしたが、その後、同様のプログラムを実施している団体と連携して実施し、昭和62年度には「共催方式」という形で、各センターの活動メニューを「活動先一覧」という冊子にまとめ、参加の広報を一緒に行うとともに、活動中の情報交換や課題についての協議を行うようになった。 平成8年度には、共催団体数は46団体、活動先メニュー数が1,536、参加者は5,616人以上にもなっている。 そして、この方法は他県へも波及し、全国的に同様のプログラムが展開されている。
こうした体験学習の参加者には圧倒的に高校生・中学生が多く、大学生の参加が比較的少なかったことから、平成5年度に「大学生ボランティア・グループ実態調査」を実施し、大学生のボランティアの活動状況と課題の把握に努めた。 その結果、大学生のボランティア・グループに横の交流を求めていることがわかり、大学生有志が企画に参加しながら、本センター主催の「第1回学生ボランティアふぉーらむ」が開催された。 その参加者のなかから、次回の実行委員会が自発的に生まれ、緩やかな学生ボランティアのネットワーク組織「学生ボランティアふぉーらむ」(以下、「学生ふぉーらむ」という。 )が誕生した。 学生ふぉーらむでは、毎年、学生のボランティア・グループの交流や情報交換の集まりと学生へのボランティア活動入門講座を企画・実施し、多くの参加者を集めてきた。 しかし、実行委員会のメンバーはそれぞれのボランティア活動をしながら、ネットワーク組織にもかかわるが負担であったことや、積極的なメンバーが卒業した後の後継者選びに苦労し、平成10年3月に解散することになった。
(9) シニアボランティア活動推進事業
高齢者の生きがいや能力活用を目的とした本事業は平成2年度から東京都の委託事業として実施されている。 その内容としては、調査、基礎講座・専門講座、関係機関・団体連絡会議、シニアボランティア交流会、啓発資料の作成、基金による活動助成と大規模なものである。 当初は高齢者の参加を目的とし、シルバーボランティア活動推進事業としていたが、退職前後の男性たちへの働きかけの必要性やシルバーという言葉の持つイメージがマイナスであることから、平成4年度から「シニア(先輩の、年配の)」という言葉に変え、事業名称を変更している。
(10) 企業ボランティア推進事業
本事業は、平成4年度に企業の社会貢献活動あるいは勤労者のボランティア活動の支援を目的として開始された。 当時、欧米社会における「企業市民」という考え方が日本においても大企業を中心に広がり、各企業からどのようにして進めていけばいいのか、その考え方やノウハウ、そして具体的な情報を求めての相談が増加していた。 また、退職前あるいは若い世代の勤労者たちが、仕事以外の自己実現や社会参加の場を求めて、ボランティア活動についての関心が高まっている時期でもあった。
事業の主な内容は、実情・意向調査やプログラム開発等の研究、企業の担当者連絡会の開催、勤労者のためのボランティア入門・体験講座の実施、啓発資料の作成等であった。
最初は大企業を対象とした事業も平成9年度より中小企業の地域社会における活動への支援へとシフトしている。
以上のように、社会のニーズに応じて、東京ボランティア・センターの事業は拡大し、その事業規模や内容、職員体制からみても日本で最大のボランティア・センターとして成長してきた。 そして、センター事業の位置づけ自体も、平成8年度には、当初の東京都から東京都社会福祉協議会への委託事業から、東京都社会福祉協議会の本来事業に対する東京都の補助事業へと移行した。