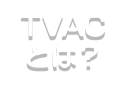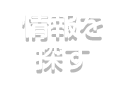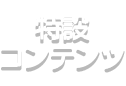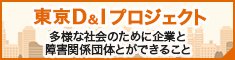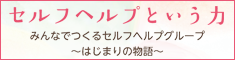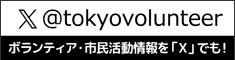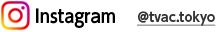TVACのあゆみ
~東京におけるボランティア活動支援の流れ~
第3章 東京ボランティア・センターの誕生
 東京ボランティア・センターの玄関。
東京ボランティア・センターの玄関。当初は東京都ボランティア・コーナーのスペースを
引き継いでいた。(後に現在の新宿区神楽河岸に移転)
1980(昭和55)年に東京都から「ボランティア・センター構想」が浮上すると、東京都ボランティア・コーナーは運営委員会の決定に基づき独自の「方策委員会」(委員長新田均日本青年奉仕協会事務局長)を設置し、その年の7月に「ボランティア・センター試案」を策定し、東京都に提言した。
そのなかで、ボランティア・コーナーの実績について、「当ボランティア・コーナーの役割は、やがて設置をみるであろう地域におけるボランティア・ビューローの望ましいモデルとしてのあり様を他に示し、また既存のボランティア育成団体やボランティア・グループに対する協力と援助を行うことにあった。 したがって、その事業内容としては、都全域に対するボランティア精神の啓蒙とボランティア人口の増大を期待し、具体的には、来所者に対する相談と助言、情報の収集と提供、場・設備・資料の提供などに力を注いできている」とした。 そして、新しいボランティア・センターの必要性としては、「しかし、ここ数年、有志グループによるボランティア活動の量的拡大と地域レベルのボランティア・ビューローの開設もすすみ、1976(昭和51)年に出された報告書〈東京都ボランティア・コーナーの現状と今後の課題〉での提言にもみられるように、地域の社会福祉協議会またはこれと同じような機能を果たしうる可能性の施設・民間団体がきめ細やかに対応できるような条件整備を具体的に考えなければならない時を迎えている。 こうした状況の変化に即応して、関係機関の競合を避け、相補い、相助けて全都的なレベルでのセンター機能を果たしていく機関の必要がいよいよ現実的なものとなった」とした。 試案はセンター構想の概要、センターの機能、センターの組織と運営、センターの設置をめぐっての4つの柱から構成されており、その運営主体としては、「本委員会は、当面、現行体制による公私協働の継続と発展を期し、その方向でセンター化を図るものとする。 ただし、長期的には、民間主体の新法人の設置もしくはそれに準ずるものの設置が望まれる」とした。
また、これと平行して、東京都社会福祉協議会も独自のセンター構想を策定し、区市町村社会福祉協議会、東京都ボランティア推進協議会、ボランティア団体連絡協議会にそれぞれ意見を求めた。 東京都社会福祉協議会の試案では、センターはコミュニティづくりを推進する拠点であり、援助機関としたうえで、区市町村社会福祉協議会が設置するボランティア・センターやボランティア・ビューローとのネットワークをもとに活動を進める点が強調された。 このため、センターではボランティの登録・あっせんは行わないとし、その主な目的は区市町村社会福祉協議会をはじめとする各種ボランティア活動推進機関・団体の活動条件の整備・強化を助長することとした。 また、社会福祉以外の分野も対象とすることや、運営委員会をボランティア関係者および学識経験者で構成し、センターの実質的運営に当たること、さらに、東京都社会福祉協議会は運営委員会に大幅な自由裁量権を付与することが述べられた。 こうした試案について、1980(昭和55)年には、「第1回センター構想検討委員会」がもたれ、関係者との協議を行った。
以上のように、ボランティア・センターの運営主体をめぐって・東京都ボランティア・コーナー側は当面、現体制のままで進むことを主張し、東京都社会福祉協議会は区市町村社会福祉協議会等との連携を強調しながら、センターの運営主体となることを求めた。 そして、東京全域の関係者を巻き込んだ協議の末、1981(昭和56)年3月に東京都ボランティア・コーナーは「発展的解消」という名のもと、東京都社会福祉協議会が運営する東京ボランティア・センターへ移行し、渋谷区美竹町に誕生することになった。